封孔処理について
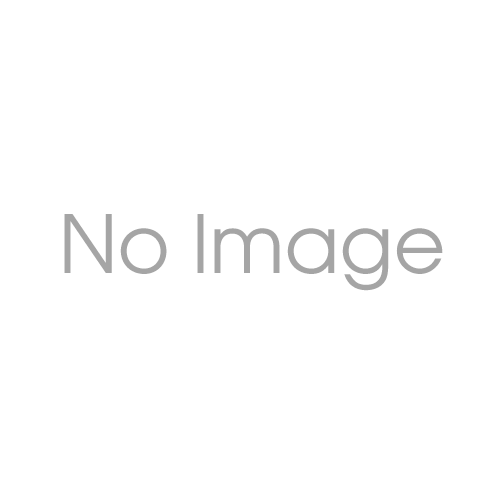
アルマイトの処理工程には「封孔」工程があります。
アルマイトに「穴」?「塞ぐ」?
一見、イメージしづらい工程にみえますが、当ブログで「封孔処理」についてご説明いたします。
封孔処理について
Ⅰ封孔処理とは
Ⅱ封孔処理の種類
Ⅲ当社の封孔処理
Ⅰ封孔処理とは
封孔とはアルマイト後にできた表面の微細孔を閉じる処理の事です。
アルマイト後のアルミニウムの表面は下のように多くの微細孔が形成されています。
(孔の数は電解液の種類・電解方法によって変わりますが、1cm²当たり4~76×10⁹個もの微細孔が形成されています。)
このアルマイト後の表面は化学的に活性なため、空気中の酸素や他の化学物質と反応しやすい状態にあります。そのため耐食性が悪くそのままでは腐食や変色等の問題が発生します。
又、化学的に反応しやすいだけでなく、多数の微細孔によって表面積が大きくなっているために物理吸着性も大きくなっています。
アルマイト処理後、封孔処理を行っていない製品に素手で触ってしまうと指紋が残ってしまい、簡単には落ちなくなってしまうのはそのためです。
(この物理吸着性と化学吸着性を利用したのがカラーアルマイトになります。他にも電解着色法、自然発色法などがあります。)
上記のような問題が起こることからアルマイト後は一般的に封孔処理が行われています。
この封孔処理を行う事により表面は化学的に安定(不活性)し、酸素や他の化学物質と簡単には反応しなくなるため耐食性が向上することになります。
Ⅱ封孔処理の種類
封孔処理の種類をご紹介します。
・蒸気法
・純粋沸騰水法
・酢酸ニッケル法
・重クロム酸法
・けい酸ナトリウム法
封孔処理の主な原理はアルマイト後の酸化被膜を水和反応させることにあります。
この水和物は化学的に安定しているため、反応が起こりにくく耐食性が高くなります。
又、水和物を生成することで表面の体積が増加し、孔が閉じられているようです。
孔を閉じることで物理吸着性も低下します。
この水和物を得るために主に蒸留水(純水)が使用されます。
水道水のままでは中に含まれる塩素イオンなどが封孔効果を邪魔して効果が得られません。
又、常温では孔壁には水和物は形成されますが耐食性を示すまでには至りません。
温度を上げるにつれ封孔効果が高まります。
(ある一定温度まで行くと効果は暫定的になります。)
そのため、蒸気や沸騰水が使用されていました。
しかし、蒸気や沸騰水を使用すると熱源が必要になりコストがかかってしまいます。
又、封孔処理時間も長く生産性が悪い状態でした。
そこで低温封孔処理というものが開発されました。
低温封孔材を使用することで常温でも封孔処理ができるようになりました。
又、処理時間も短くなっています。
Ⅲ当社の封孔処理
一般的に封孔処理を行うと硬度が低下してしまいます。
せっかくアルマイト処理で硬度を高めても硬度が落ちてしまっては意味がありません。
当社のアルマイトは一般的なアルマイト処理を行ったものよりも硬度が高い事が特徴です。
普通アルマイトではHv150前後が一般的ですが、当社の普通アルマイトではHv200~250ほどになります。ウルトラハードではHv500近くまで高めることができます。
又、封孔処理を行うと粉吹きが発生してしまいますが、当社の封孔処理は適切な封孔材の
管理・処理を行っているため粉吹きがほとんど起こらない事が特徴です。
アルマイト処理は皮膜を生成する事 と見られる事が多いですが、
このように、後加工にも技術・ノウハウがあります。
当社でも「封孔処理」のノウハウを用い、最適品質のアルマイト製品をご提供しております。
アルマイト加工に関するご相談は
日本伸管にお任せください
お電話でのご相談の場合はこちら
048-477-7331
受付時間:08:30~17:30(土・日・祝日は除く)


.png)
